AsについてQ&A(FAQs)(new!)
asについて1
asは多義語でわかりづらいです。asは1語なのになんでそんなに沢山意味があるのですか?
asは1語です。
ですから<strong><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">=(イコール)</span></strong>のたった1つのイメージで全て解決できます(1対1の対応です)。
多義語?
そんなことはありません。
受験生にも、たくさんの意味を丸暗記した社会人にも役立つはず。
以下、ぜひFAQsの説明でご確認ください。
He is not as tall as I.「彼は私ほど背は高くない」はHe<Iです。notを取るとHe≧Iになるはず。なのになぜHe is as tall as I.は「彼と私は同じ背だ」He=Iになるのですか?
=は<span style="color: #ff0000;"><strong>「匹敵するくらい」</strong></span>です。
He is not <strong><span style="color: #ff0000;">as</span></strong> tall/ as I.「彼は<strong><span style="color: #ff0000;">匹敵するくらい</span></strong>背は高くない/私に」
He<Iです。
notを取ります。
He is <strong><span style="color: #ff0000;">as</span></strong> tall / as I.「彼は<strong><span style="color: #ff0000;">匹敵するくらい</span></strong>背が高い/私に」
He=Iですね。
はい、簡単に解決しました。
他にも「肩を並べるくらい」とかでもいいですね。
肯定で同じ、否定で負けている感じになります。
同類の意味の言葉でasは理解してください。(他にもあるかも知れません。)
いずれにせよ「同じ」ではダメなのです。
(He is not as tall as I.「彼は私と同じ背ではない」……どっちが高いか分からないからダメです。=はas〜asという比較の構文の中では「匹敵するくらい」[or類する表現]一択です。)
※以下、塾長の愚痴です。読み飛ばしてください。すみません。
一部トップ講師と呼ばれる方々はasが≧だと言っています。
彼らの本にも同様の記載があります。
しかしasが≧なんてことは<span style="text-decoration: underline;">絶対に</span>ないです。
複雑怪奇な考え方で、お話になりません。
一方でasが「匹敵するくらい」はシンプルで普遍性があります。
asと同語源のalso「〜もまた」も=のニュアンスであって、決して≧ではありません。
My girlfriend was also called Helen.「私のガールフレンドもまたヘレンという名前だった」
alsoはイコールであって、≧ではありません。
asだってそうです。イコールです。
≧のわけがないのです。
日本人は批判精神が弱く、権威に従順なために無批判に受け入れてしまうのでしょうが、そろそろ考えをお改めになったほうが良いと思います。
英語の権威は往々にして間違いが多い。
だから日本人は英語ができない。
腑に落ちると思います。
彼らが正解を言っているなら、日本人がこんなに英語がダメダメな訳はないでしょう。
彼らでさえダメだから日本人全体もダメなのです。
私が日本でもっと評価されるようになったら日本人の英語力も上がっていることでしょう。
このページをも批判的に読んで、思考回路をしっかりとしたものにしてください。
日本で一二を争う批判的精神を持った池田英語塾を批判的に読む。
これこそ英語制覇の第一歩ですよ。
asについて2
asが≧だ、と言っている有名英語講師が書いた本が何冊もあるのですが、それって合ってますか?
合ってません。
He is not as tall as I.「彼は私ほどの背ではない」He<I
ここからnotを取れば逆の≧になるはずだ、という数学的な考え方でそう言っているのだと思います。
asに関しては残念ながら数学のように英語はいきません。
「匹敵するくらい」で簡単に解決します。
数学的に考えて…なんて疲れることは止めましょう。
(あとで、めぼしい本に書いてあることに全て検証を加えていきます)
間違えているのに本を出せて、生徒さんたちに絶賛されて羨ましい限りです。
生徒さんたち、先生が間違えているのに、なぜ絶賛するの?
日本国内でその態度は通じても、世界では通用しません。
世界ではasは≧で捉えていないからです。
asがなぜ「〜する時」の意味になるのですか?
<strong><span style="color: #ff0000;">As</span></strong> I entered the room, they applauded.
「私が部屋に入った」<span style="color: #ff0000;"><strong>=</strong></span>「彼らが拍手喝采した」
→「私が部屋に入った」<strong><span style="color: #ff0000;">「それとイコールで」</span></strong>「彼らが拍手喝采した」
→「私がその部屋に入った<strong><span style="color: #ff0000;">時に</span></strong>、彼らは拍手喝采した」
asが≧では「私が部屋に入った、それと同じかそれ以上で、彼らが拍手喝采した」???訳分かりません。
「asは=」です。
それだけで全て解決します。
(「asについて」の例文は全てジーニアス英和辞典からの引用です)
asについて3
asがなぜ「〜につれて」の意味になるのですか?
「asは=」です。
As the sun rose, the fog disappeared gradually.「太陽が昇るにつれて、霧が徐々に晴れた」
「太陽が昇った」=「霧が徐々に晴れた」なら確かに「〜につれて」だと分かります。(asが比較級と一緒に使われている時、「〜につれて」になることが極めて多いです)
「太陽が昇った、それと同じかそれ以上で、霧が徐々に晴れた」では意味がわかりません。
asが「同じかそれ以上」というのはおかしいと思います。
asがなぜ「〜だけれども」の意味になるのですか?イコールだと言うならおかしくありませんか?
全然おかしくないですよ。
Asが「〜だけれども」というのもイコールで説明がつきますが、これはwhileが「〜である一方で」という対比の意味と絡んできます。
脱線しますが、whileがなぜ対比になるのかをまず説明します。
英語は2つのことが同時に起きている場合、対比を表します。
while〜「〜している間」は2つのことが同時に起きていることを表します。
だから対比「〜の一方」「その一方」を表します。
(例文)While he is respected, he is not liked.「彼は尊敬されている一方で、好かれてはいない」。
「尊敬されている」と「好かれていない」が「同時」に起きています。
それゆえ対比(=「その一方」)だとわかります。
Asはイコールですから、2つのことが同時に起きていることを表します。
それ故、asが対比の意味を表し日本語で「〜の一方で」「〜だけれども」と訳されるのです。
Men usually like wrestling, as women do not.「女性はレスリングは好きではないが、男性はたいてい好きだ」。
「男性がたいていレスリングが好きだ」というのと「女性は好きではない」というのがasで同時に起きていることが表現されています。
二つのことが同時に起きているので対比(「〜の一方で」「〜だけれども」)になっています。
これでも怪しいと言うならat the same timeを辞書で引いてみてください。
ジーニアスならsameで引いて、成句のところでat the same timeを見てください。
(1)同時に(2)でもやはり、けれども、と出ています。(He can be rude; at the same time everyone likes him.「彼は失礼なことをすることもあるが、その一方でみんな彼が好きだ」)
(2)が対比の意味を表しています。
ただasが「〜だけれども」というのはやはり気づきにくいかもしれないという事で、Good as he is, he will never come out at the top of his class.「彼はいい生徒だが、決してクラスのトップにはなれないだろう」のように語順を変えて気づきやすくすることが多いです。
無冠詞の名詞as SV〜とか形容詞as SV〜とか副詞as SV〜の形になります。
ただこの形でも稀ですが「〜なので」になることがありますので、文脈に十分に注意してください。
これでご納得いただけましたか?
世界中どこを探してもこの件を解説している本はありません。
英語に関してはどの組織よりも池田英語塾をどうぞ信頼していただけると塾長、大喜びいたします。
asについて4
asになぜ「〜なので」の意味があるのですか?
asは=です。
As I didn't have any stamps, I couldn't mail the letter.「切手がなかった」=「手紙を出せなかった」
→「切手がなかったので、私は手紙が出せませんでした」となります。
「切手がなかった」≧「手紙を出せなかった」………私には意味がわかりません。
面倒な≧はやめましょう。
偉い先生が言っているからこそ止めるのです。
偉い先生が言っても間違いは正解にはならないのです。(学校の定期テストでは先生が言うと間違いでも正解になることはよくありますが。「s-で始まる頻度の副詞を書け」という問題でseldomを書いた帰国子女。×でした…。教科書にはsometimesしか書いてないからseldomはバツなのだそうです。……そんなわけあるかーい!💢)
asに「〜なように」の意味があるのは…一応説明してもらえますか?
もちろんです。
Do as I do.「 私がするようにやりなさい」
Do「しなさい」=I do「私がする、とイコールで(匹敵するくらいで)」
これで「私がするようにやりなさい」となりますね。
また≧を検証します。
Do「しなさい」≧ I do「私がするのと同じかそれ以上で」ではお手本の「私がする」以上のことをしてしまいます。
失敗してしまいそうですね。
≧は間違ってますよ、絶対に。
(間違っていることをお偉い方々が言うのが本当にストレスです。そういう方々の本で勉強している方々は、私の言っていることを間違いと考えてしまう。本当にストレスです。正しいのは池田英語塾です。キリスト教ではありませんが、池田を信じる者は救われます。どうぞ信じてやってください)
asについて5
not as〜as…がなぜless〜than…になるのですか?
He is <span style="color: #ff0000;"><strong>not as</strong></span> tall/as I.「彼は<strong><span style="color: #ff0000;">匹敵するほど</span></strong>の背の高さでは<span style="color: #ff0000;"><strong>ない</strong></span>/私に」
「<span style="color: #ff0000;"><strong>匹敵するほど〜ではない</strong></span>」ということは「<span style="color: #ff0000;"><strong>劣っている</strong></span>」ということ。
だからHe is <span style="color: #ff0000;"><strong>less</strong></span> tall/than I.「彼は<strong><span style="color: #ff0000;">劣って</span></strong>背が高い/私より」と<strong><span style="color: #ff0000;">劣等比較</span></strong>(=<span style="text-decoration: underline;">less原級</span>のこと)で表現できるのです。
※劣等比較とは:
<strong><span style="color: #ff0000;">less</span></strong>はlittle「ほとんど〜ない、少ない」の比較級です。
ですから「より少ない」「より少なく」です。
<strong><span style="color: #ff0000;">less<span style="color: #000000;">原級</span></span></strong>の形で以下のような意味になります。
This flower is <span style="color: #ff0000;"><strong>less</strong></span> beautiful /than that one.この花は<strong><span style="color: #ff0000;">より少なく</span></strong>美しい/あの花より。→この花はあの花ほど美しくない。
このようにless原級で、<span style="text-decoration: underline;">より劣っている</span>ことを表すので「<strong><span style="color: #ff0000;">劣等比較</span></strong>」と言います。
倍数表現でasが使われるのがわかりません。twice as 〜「2倍同じ〜」って…何ですか?2倍なのですか?同じなのですか?
<span style="color: #ff0000;"><strong>as</strong></span>は「同じ」ではありません。(偉い先生が本で書いてますが「なんとなく等しい」も一見素敵な考えのようでいて、実際は通用しません。)
「<strong><span style="color: #ff0000;">匹敵するくらい</span></strong>」です。
He has<strong><span style="color: #ff0000;"> twice as</span></strong> much money /as I.
彼は<strong><span style="color: #ff0000;">2倍に匹敵する</span></strong>お金を持っている/私の。
これなら「2倍なの?」「同じなの?」という疑問は生じませんよね?
「彼は<strong><span style="color: #0000ff;">2倍同じ</span></strong>お金を持っている/私と」
「彼は<strong><span style="color: #0000ff;">2倍なんとなく等しい</span></strong>お金を持っている/私と」
……これだとご質問の通り、2倍なのか同じなのか、なんとなく等しいのか訳わかりません。
「なんとなく」意味はわかりますが、しっくり来ません。
不完全。
間違いなく「<strong><span style="color: #ff0000;">asは=</span></strong>」「<strong><span style="color: #ff0000;">=は匹敵するくらい</span></strong>」です!!
これ以外は信じる必要はありません…というより信じてはなりません!
asについて6
as〜as anyって何ですか?
Jack is <span style="color: #ff0000;"><strong>as</strong></span> intelligent /<span style="color: #ff0000;"><strong>as</strong></span> <strong><span style="color: #ff0000;">any</span></strong> boy /in his class.
ジャックは<span style="color: #ff0000;"><strong>匹敵するくらい</strong></span>頭がいい/<strong><span style="color: #ff0000;">どんな</span></strong>少年<span style="color: #ff0000;"><strong>にも</strong></span>/彼のクラスの
→「ジャックは彼のクラスのどんな少年にも頭の良さでは<span style="color: #ff0000;"><strong>負けていない</strong></span>」
すごい優秀だが、圧倒的ではない、単独一位という訳ではないが、ただ他の誰にも負けていることはない、と言う表現です。
この時に限っては「Jack≧他の少年たち」というニュアンスも無くはないかもしれません。
「どんな少年にも匹敵するくらい」ということは、同率一位で、単独一位ではないけど、雰囲気として「もしかしたら勝ってるかも」というニュアンスはもしかしたらありそうです。
でもこのことでasは≧だ、ということはありません。
as 〜as anyだから、すなわち<span style="text-decoration: underline;">anyが加わったから</span>≧と言えなくはない、程度のニュアンスです。
as単独で≧は表していません。
anyが加わることでようやく≧のニュアンスが入ってくるかな、ということは、as単独が≧でないことの証明でもあります。
asは単独ならあくまで「匹敵するくらい」です。
asが単独で≧を意味することは<span style="text-decoration: underline;">絶対に</span>ありません!
asを≧と言っているミスリーディングな本の名前を教えてくれますか?
はい、承知しました。
まずは「真・英文法大全」(関正生、KADOKAWA)
<img src="https://reading-pro.net/wp-content/uploads/IMG_0886.png" />
「英文法の核」(西きょうじ 東進ブックス)
<img src="https://reading-pro.net/wp-content/uploads/IMG_8241-scaled.jpg" /><img src="https://reading-pro.net/wp-content/uploads/IMG_8242-scaled.jpg" />
しかしメチャクチャな論理展開です。
>「ローラは魅力的だよ、少なくともアンくらいにはね」というニュアンスを<span style="text-decoration: underline;">含むこともあります</span>。
どこから「少なくとも」が出てきたのでしょうか?
全く私には読み取れません。(≧ありきで考えていただけだと思います)
>というニュアンスを含むこともあります。
ということは、<span style="text-decoration: underline;">たまにそういうこともあるかもしれない</span>、ということですね。
>そうするとこの文はLaura≧Annということを表している<span style="text-decoration: underline;">ことになります</span>。
…論理が破綻しています。
どこから出てきたかわからない「少なくとも」で、勝手に>と決めつけ、≧とするって…
それに加えて、<span style="text-decoration: underline;">たまにそういうこともあるかもしれない</span>ことが、<span style="text-decoration: underline;">常にそうだ</span>、と話がすり替わっています。
たまにそういうこともあるかもしれない例を具体的に挙げると……
大谷翔平がたまには10打席連続凡退をすることもあるかもしれない。
なのにそれを根拠に大谷翔平が常に凡退する、と言っているようなものです。
めちゃくちゃです。
「少なくとも」などというニュアンスは全くないし、「たまにそうかも」を根拠に「常にそうだ」というのは西先生、残念ながら違うと思います。
西先生はこういう論理展開が非常に多い。
スラッシュリーディングは「10キロの道のりをジェット機で行くようなもので、受験では必要がない」のだそうですが、ちょうど10キロほど離れているところから新潟予備校に通っていた生徒さんの一言が全てを論破します。
「10キロの道のりをジェット機でいけたらいいっすよね‥」
新潟予備校時代から感じていて、こういう先生に長岡高校の後輩たちが習っているということに忸怩たる思いをしていました。(当時西先生は代ゼミ新潟校の看板講師。私は新潟予備校の基礎クラスの看板講師。あ、新潟予備校の方が生徒数は代ゼミより多かったんですよ。新潟予備校の勝ちです。黒字のうちに休校しましたけどね。)
「竹岡の英文法・語法ULTIMATE究極の600題」(竹岡広信 学研)
<img src="https://reading-pro.net/wp-content/uploads/IMG_8238-scaled.jpg" /><img src="https://reading-pro.net/wp-content/uploads/IMG_8239-scaled.jpg" />
竹岡先生がここまで明らかなミスをされるのも珍しい。
鉄緑会が東大の要約問題で正解としている解答を10点中4点とされたのは痛快だったが…(2005年度の問題です。「東大の英語25ヵ年」[教学社]。ただ私はもっと点数低くつけます。鉄緑会の英語はもう少し頑張りましょう。「鉄壁」の中でattachのtachはtouchではなく「杭」ですよ。辞書を引きなさい。情けない。それを評価している世の中の受験生も情けない。東大理三であっても間違いは間違いです)
先生の考え方だとasが非常に面倒なものになります。
「曲を書く際に、私は匹敵するくらい多くを学んだ/セザンヌから/モーツアルトから、に」→
「曲を書く際に、私はモーツアルトからも学んだが、それに匹敵するくらい多くをセザンヌからも学んだ」
文脈を見ないと断言はできませんが、セザンヌは一般人ではなく、印象派の画家の可能性が高いと感じます。
音楽家からも学んだが、それに匹敵するくらい画家からも学んだ、というのは十分にありうることです。
残念ながらasに関しては間違えられていると思います。
すごい先生まで間違えさせてしまうくらいasが≧というのは間違っていて複雑怪奇な考え方です。
従順な進学校の生徒さんたち(筑駒、灘、開成、桜蔭、女子学院,etc)が苦しんでいたら即刻この考え方は捨てた方がいいですよ(こういう学校の方々の方が英語がダメ。複雑に考えすぎ。長岡高校の軍門に下ってください。一応全国模試で英語1位を取ったこともある人間です。わかりやすく解釈できることを約束しましょう)。
でも「東大の英語」わかりやすく助かりました。
うちの東大受験生で使わせて頂いております。
ありがとうございます。
asについて7
as〜as ever lived「古来まれな〜」「並外れた〜」って何ですか?
これも<span style="color: #ff0000;"><strong>as</strong></span>「<span style="color: #ff0000;"><strong>匹敵するくらい</strong></span>」で解決です。(「<span style="color: #333399;">同じかそれ以上</span>」は散々証明してきましたが<span style="color: #333399;">ダメ</span>です。)
辞書の例です。
上がジーニアス英和辞典、下がランダムハウス英和大辞典です。
<img src="https://reading-pro.net/wp-content/uploads/IMG_9583.jpeg" /><img src="https://reading-pro.net/wp-content/uploads/IMG_9584.jpeg" />
He is as great a scholar/ as ever lived.「彼は匹敵するくらい偉大な学者だ/これまで生きた、に」
英語は比較される二者は必ず同種のものという大前提があります。
ですから上の文章でも、「彼」という偉大な学者とever lived「今まで生存した<span style="text-decoration: underline;">学者たち</span>」を比べているということになります。
これまで生存していたどんな学者にも<span style="text-decoration: underline;">匹敵する</span>偉大な学者なので、「彼は古来まれな学者だ」「彼は並外れた学者だ」「彼ほどの学者はいない」(以上ジーニアス英和辞典)、「彼は今まで生存した誰にも劣らず偉大な学者だ」「彼はこの上なく偉大な学者だ」(ランダムハウス英和大辞典)となります。
上の文章の"He"をアインシュタインと仮定しましょう。
アインシュタインがどんなにすごくても、生きている当時のアルキメデスの業績、ニュートンの業績と比べてどちらが上と判断がつかない。
アインシュタインの発見だってアルキメデスやニュートンの発見、業績があってこそで、どちらが上とはいえない、どれもすごい、という表現です。(ただここはアインシュタインが主語なので、「アインシュタインはすごい!」というのが主題になりますが)
asは=「匹敵するくらい」です。
池田英語塾のみが気づいている言葉のようですが、どうぞ皆様おつかいください。(一般の方々、小さな塾の先生方もどうぞ。大手予備校の講師は禁止。出典を言ってください。)
全てが解決できますよ。
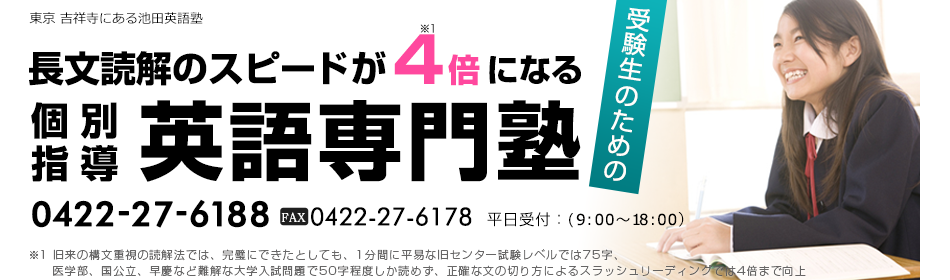
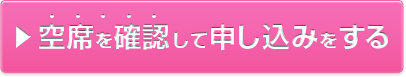

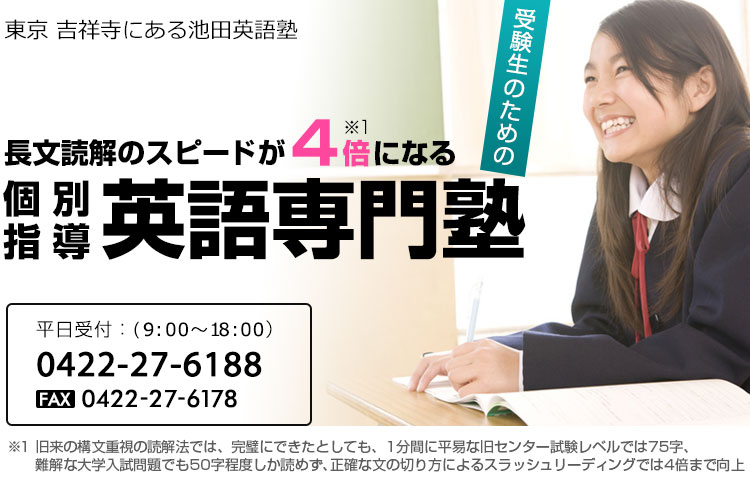

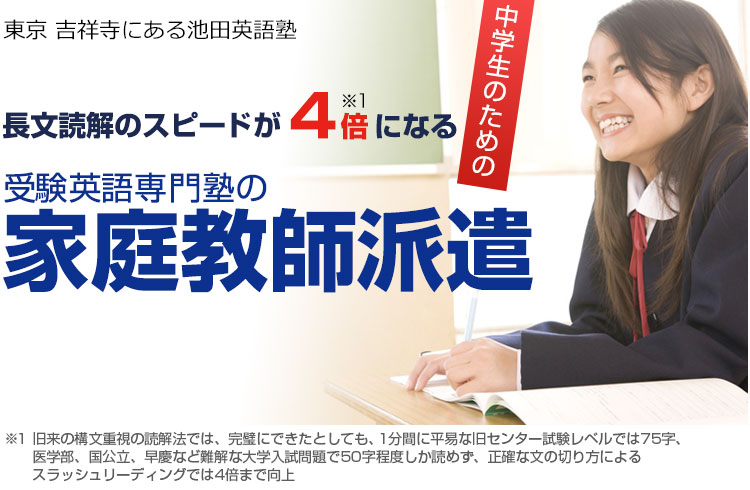

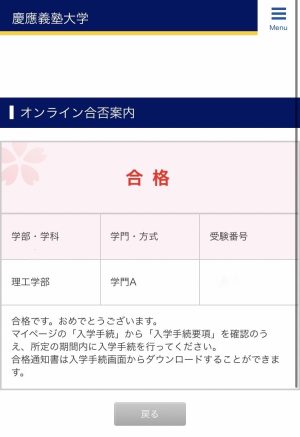
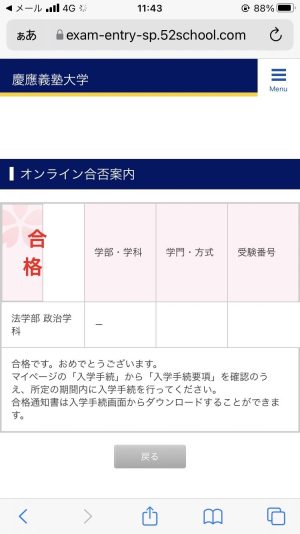
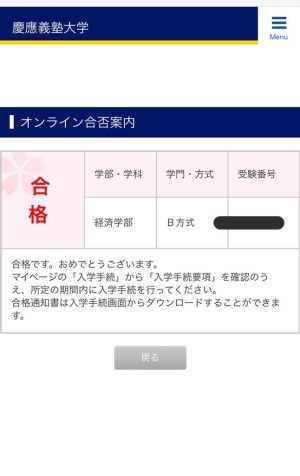
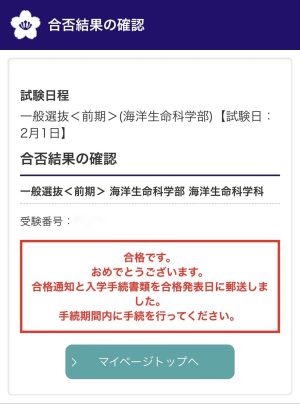 東京女子大(数理科学学科数学専攻)東海大(海洋学部海洋理工学科)成蹊大(理工学部データ数理)東邦大(理学部生物学科、生物分子学科)
東京女子大(数理科学学科数学専攻)東海大(海洋学部海洋理工学科)成蹊大(理工学部データ数理)東邦大(理学部生物学科、生物分子学科)